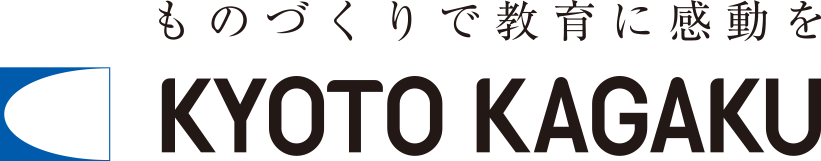- 院内教育
- 新人看護職員研修
- 看護教育
現場の指導力を上げる!
看護実践力の向上に取り組む沖縄のシミュレーション教育【後編】
沖縄県内でシミュレーション教育に関心のある有志で活動している「看護実践力を育む研究会」。そのメンバーの一人である社会医療法人友愛会 人事部人材開発課 課長 池田晴美氏と、現場で指導されている友愛医療センター 看護部 教育担当統括師長 洲鎌陽子氏に、看護実践力を育む研究会(以下、研究会)と院内の看護教育についてお話を伺いました。
※この記事は「新人看護職員研修 教材カタログ2021年度版」に掲載の記事をWEB用に書き起こしたものです。

院内研修について
Q.指導者の育成は、現場でどのようにされていますか?
誰もが指導できるように
池田氏: 現場においては、看護方式をPNS(パートナーシップナーシングシステム)に変えて、現場で先輩後輩なく意見を言い合える風土を作りながら学んでいくというスタイルにしています。シミュレーション教育を重要だと思いつつも、全員が研究会に参加できる状況ではないですし、皆が100%取り組めるわけではない中で、指導者を育成していかなければなりません。そのために枠組みをつくって院内研修を行いながら現場レベルで指導力を上げていくことが重点課題かなと思っています。
― 重点課題と思われるのは、現場の研修担当が短い期間で変更になることも関係するのでしょうか?
洲鎌氏:与えられた仕事をやればいいという考えの職員もいる中で人を育てるという意識改革から始めるには、研修を担当している期間は短いのかもしれません。でも同じ人がずっと居るわけでもないし、誰もが指導できるというような状況に変えていくにはもう少し時間がかかると思いますね。短いからできないわけでもないし、難しい部分ですが、誰でもできるという風土に変えていく必要があると思います。
池田氏:ある一部の指導者がトレーニングを受けて優秀な指導者になることは、組織全体で見ると一部だけが活動しているに過ぎません。それだとなかなか風土の変化には持っていけないと思って。だから新人さんのシミュレーション教育を部署でできる状況にしたくて、集合研修の検温トレーニングを4月の夜勤が始まる頃に行っています。このトレーニングは現場の先輩たちがシミュレーションを行う形式で、指導者のスキルもそこで上げていきながら進めています。あとは教育担当の指導者だけ頑張ればいいというのではなくて、パートナーシップナーシングをやる中で、パートナーになる相手のことをちゃんと思いやってお互いが能力を発揮できるような関係性の構築を目指したいという理想はあるんです。
Q.新人看護職研修で研究会の内容が役立ったところはありますか?
各部署でシミュレーション研修を実施
洲鎌氏:部署で研修をやるところまで持っていけたことですね。池田課長はじめ師長たちも何人か研究会に参加して、それをもとに中堅スタッフたちが部署で頑張った成果だと思います。
池田氏:先ほどお話した「夜勤前の検温トレーニング」は、シチュエーションベースドトレーニングという捉え方になります。そこでは、あらゆる現場の中で起こり得ることを想定して、シミュレーションを行います。教える側も模擬患者役などで参加して進めます。
「夜勤前であれば、こういうところに気をつけて欲しいこと」を単にオリエンテーションするだけでなくて、シミュレーションを通して新人さんに伝える、気づきを与えることが教育に役立っていると感じています。

コミュニケーションから生まれる気づき
洲鎌氏:もう一つは先輩と後輩のコミュニケーションですね。
池田氏:日々の業務の中だけではなくて、研修で直に教えると先輩が考えていることや、後輩が考えていることも聞くという相互作用が出てくるので、そこからコミュニケーションが広がるのは大きいと思います。
気づいたことを伝えるというのは業務の時間内だと難しいんですね。だからシミュレーションという時間軸がゆっくりしている中で話し合いをしていくと、1年生は「先輩たちが伝えたかったことはこういうことだったんだな」という気づきがシミュレーションを通して理解できると思いますね。
洲鎌氏:現場だと、先輩は1年生が何を考えているかを聞く機会がなく、1年生も自分の考えを整理する時間もないので、考えを引き出すのが難しくて。シミュレーション教育の中だと「あ、先輩ってこういうふうに考えるんだ」とか「1年生はこう考えているんだ」と気づけることが、先輩たちにとってもいいことだと思ってます。また、1年生同士でも違う人の価値観を学べて業務に活かせるということをよく聞きますね。
池田氏:一人で考えて学んでいく力よりも同期の子たちと一緒に学びながら育っていく環境があると、成長速度が早くなるのかなと感じますね。

Q.今後の展望をお聞かせください
自信を持って自立(自律)できるような研修に
洲鎌氏:新人さんが働き続けられて自立(自律)できるような研修内容にできればいいなと思っています。看護の仕事は自分で考えることや責任を伴うことが多く、自分が行った看護の先には命があるので、やはり自立できないと困るというのがありまして。新人さんの自立を目的に輪を広げていきたいなと常々思ってます。
池田氏:プロフェッショナルであることを求められる仕事なので、1年生となって患者さんと対峙した時に、すごく戸惑ったり困ったりして「私には無理なのかな?この仕事合わないのかな?」と考えがちです。そういう時に「そうじゃないよ」と。「できること増えたよね。やれることはひとつひとつクリアしていってるから、焦らずゆっくり成長しようね。そのために研修でサポートはしていきますよ。だから大丈夫よ。」というサインを送り続けるってすごく大事かなと思います。看護職は、患者さんの安心安全を守らなければらないので、自分自身で勝手に判断してもらっても困るけど、自己評価があまりにも低すぎてやらない、先輩の後ろを追いかけきれないというのもやはり困るんですね。だから自分自身で考えて判断をし、自分の限界が今どこまでなのかというサインを本人たちがしっかり先輩たちへ送って、サポートや援助を求めていくことがすごく大事になってくるんですよ。だから、できないことを羅列させていくというよりも、できることに自信をつけさせたいですね。
この度はお忙しい中取材にお応えいただき、ありがとうございました!「沖縄は情報を得ようとしても県外へ気軽に行けない場所なので、県内で情報共有して一緒に頑張る取り組みをしている」というお話が印象的でした。
 |
取材ご協力:社会医療法人友愛会 友愛医療センター (2020年8月移転時に豊見城中央病院より名称変更) 病床数:378床(再生医療戦略特区許可病床2床含む) 地域医療支援型病院 地域災害拠点病院 基幹型臨床研修病院 沖縄DMAT指定病院 救急告示病院 *2019年度実績 病床利用率:91% 平均在院日数:9.6日 外来患者数:870名/1日平均 入院患者数:344名/1日平均 |
 |
取材ご協力: 人事部人材開発課 課長 池田 晴美 氏 看護部教育担当統括師長 洲鎌 陽子 氏 看護部新人教育担当師長 岡部 真理子 氏 看護部新人教育担当師長 仲本 エリ子 氏 |