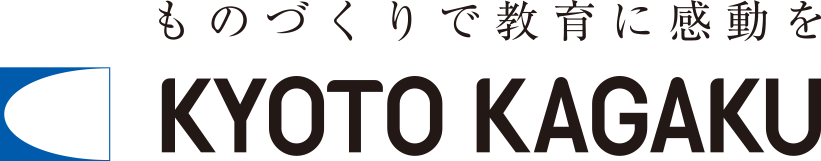- 放射線防護
- 放射線診療
- 医療従事者の安全管理
放射線防護を
演習を通して身につける
手術中のエックス線透視やポータブルエックス線撮影装置使用時のサポートなど、放射線室以外でも医療従事者が放射線に接する機会は日常的にあります。一方で、放射線は危険なもの、浴びれば健康被害をもたらすもの、というようなイメージが先行している傾向にあります。合理的かつ安心安全な医療を提供し、また自身を守るために、医療従事者が放射線を正しく理解し適切な防護をすることが求められています。
今回は放射線防護教材の開発にご協力いただいた小野孝二先生にお話を伺いました。
*この記事は「看護師等養成所 教材カタログ2024年度版」に掲載の記事をWEB用に書き起こしたものです。

放射線防護教材 開発の経緯
2020 年のカリキュラム改正において、到達度を示す「技術」は手技であると整理され、必ず演習で実施することが示された。一般社団法人 日本看護学校協議会では、会員校への71 項目の実施状況調査(2019,20 年)の結果をもとに、学内演習の実施率が低い項目に対する演習支援教材開発プロジェクトが立ち上げられた。そのうちの1 つ、「放射線防護」について、日本看護学校協議会と京都科学は東京医療保健大学の小野孝二先生に監修をいただき、医療従事者向けの放射線防護教材を開発した。

適切な防護って、なんだろう?
医療従事者への放射線教育は、養成所での基礎教育を最後に、その後は個人や施設に委ねられています。放射線を専門としない場合は一度臨床に出てしまうと知識がアップデートされる機会が少ないため、現場では適切ではない防護が実施されていることがあります。
「適切でない防護」と聞いて、防護不足による医療従事者の被ばくを想起された方も多いでしょう。しかし、放射線を恐れるあまり、必要以上に防護策を取ってしまう過剰防護もまた問題です。
例えば、病棟でポータブルエックス線装置を使用する際、介助にあたる看護師が撮影時にエックス線装置から過剰に” 避難” したり、妊娠している同僚に「あなたは妊婦なのだから部屋から出ていなさい」と発言したとします。その時、カーテンを挟んで隣のベッドに寝ている他の患者はどう思うでしょうか。また、撮影されている患者は、エックス線撮影を受けるメリットと被ばくのリスクを正しく天秤にかけることができるでしょうか。
防護不足が医療従事者本人の健康のリスクになる一方、過剰防護は合理的な業務、そして患者が安心して治療を受けられる環境づくりの妨げになる可能性があります。医療従事者は放射線の正しい知識を身につけ、患者にも自分自身にも過不足ない放射線防護を実施しなくてはなりません。
そのためにも、養成所教育の中で限られた時間の中で、いかに学生に放射線の本質を理解し基礎を身につけてもらうかが重要なのです。
「なんとなく」ではなく、根拠をもった防護策を
この教材では、医療従事者が放射線を正しく理解し、根拠をもって自身を防護できるようになることを目標としました。
第1章 「放射線の基本的知識」
第1章の「放射線の基本的知識」では放射線の種類やBq(ベクレル)Gy(グレイ)Sv(シーベルト)など放射線の単位や、どの程度の放射線量で健康に影響が出てくるのか、基準となる値(しきい値)をステップバイステップで解説しています。
放射線の基礎知識は数学的かつ普段聞きなれない用語が頻出するため難しく、実践的な防護策までスキップしたくなるでしょう。しかし、単位の概念が理解できるようになると、放射線の数値を目にした際、この放射線がどの程度人間に影響を与えるのか、そのリスクを自分で評価できるようになります。
このDVDでは、私のこれまでの経験から、初学者がつまづきやすい部分にはイラストやアニメーションを用いて、視覚的に分かりやすく、かつ簡潔に説明しています。
第2章 「放射線の医療安全」
第2章「放射線の医療安全」では、医療従事者の線量限度や防護、線量計の付け方、国試の過去問など、第1章の知識をもとに、より実践的な内容に踏み込んでいます。
第3章 「放射線防護のための演習」
第3章「放射線防護のための演習」では、4つの実験を収録しました。うち3つの実験は実験セットを用いて実際に演習いただけます。線量計を用いて線量を測定することで、放射線防護の3原則である、「時間」「距離」「遮蔽」をただ暗記するのではなく、体験を通じて理解し、行動してもらいたいです。
セットを使って実験してみよう!
ここからは、教材を用いた演習の様子をご紹介します。
①まずは、DVD視聴!

学生の集中が切れてきたら実験を先に挟んだり…。様子を見ながら進めます
②自然放射線の測定実験

地面からの年間被ばく量はどのくらいだっけ? DVDで学んだ知識と計測値を比べてみます
③DVDの内容に沿って、距離と遮蔽の実験

学内で卒業前にアンケートを取ると、記憶に残った演習の上位に放射線実験がランクインしていました
④付属のワークシートに実験結果を記録

グラフが出来上がると、放射線の特性が見えてきます
参加者の声
病室内でX線検査をする際、散乱線は100 μ Sv で微々たるものであることを理解した上で公衆被ばくする周りの患者への説明をしたり、MRI検査の前に金属類を着用していないか確認したり、家族が放射線の不安を訴えたら、科学的な知見から安心させたりすることが看護師には必要だと学んだ。
参加者の声
防護具を使用すればある程度防げる、、という漠然としたイメージを持っていましたが、今回の講義で具体的にどの程度防ぐことができるのか、距離に比例して減少する線量などについて学ぶことができ、具体的な知識を得ることができました。
教材指導
 |
小野 孝二 先生
東京医療保健大学 |
学校紹介
 |
東京医療保健大学 国立病院機構キャンパス 東が丘看護学部 東京医療保健大学は、5 学部7 学科、2 専攻科及び大学院修士課程・博士課程を有する医療系大学です。 「多様な価値観を尊重し、一歩先を歩み続ける開かれた大学」を目指し、全学一丸となって教育・研究・社会貢献に取り組み、明るい未来の医療保健を創造します。 |